
数と空間を研究し創造する楽しさ
数学は既に出来上がってしまった学問でなく、
日々「進歩・発展」を積み重ねていくもの。
代数学・幾何学・解析学が相互に融合し発展する現代的で
美しい理論、単なる計算技術ではない
本物の数学を身近に感じてください。
専門科目
【線形代数】【微分積分】【集合と位相】【曲線と曲面】
【複素関数論】
【代数学】【測度と積分】【位相空間】
【確率】【アルゴリズムと計算】

- 海外の研究者との共同研究が、活発に行われている学科です。
様々な分野の研究者が、ここ学習院大学数学科を拠点とし、研究活動や教育活動を
行っています。 -
人に「感動」や「楽しさ」、「気づき」を与えられる数学の面白さ。

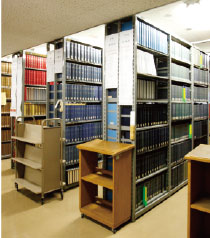
-
私は中学の頃から教師になりたいという思いがありました。周りの友達で数学に対して苦手意識を持っている人が沢山いたのですが、そんな友達が「わかる喜び」や「考える楽しさ」を感じてくれた時、とても嬉しかったのを覚えています。
大学進学後、1年生と2年生では必修科目が多く、数学の基礎となる分野を幅広く学びます。高校数学までは定義や公式を覚えれば解ける問題が多かったのに対し、大学数学ではそれぞれの分野の理論的背景を理解し、問題を解く過程や証明に重点を置くため、数学という学問の奥深さを実感することができます。3年生になると選択科目が増え、4年生で所属するゼミに向けて、興味のある分野をさらに深く学んでいきます。学年が進むにつれて、難易度や学問の深さに対する意気込みは高まり、数学に対する探求心も一層強くなりました。毎日の学びが積み重なっていく中で、数学の面白さや奥深さをさらに感じています。
将来の夢は数学の面白さを伝えられる教師になることですが、実はエンタメの分野にもとても興味があります。一見、対極にある世界のようですが、実際にはどちらも人に「感動」や「楽しさ」、「気づき」を与えられるという点では共通しており、私にとってはどちらも惹かれる世界です。
-
-
自分が興味のあることを、好きなだけ突き詰めることができる環境。
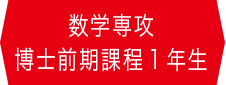

-
現在、樋口教授の研究室に所属し、グラフ理論の研究を行っています。グラフ理論とは点(頂点)と線(辺)を使ってさまざまな関係性やネットワークを表す数学の分野です。私はグラフ理論を使って「peg solitaireゲーム」というボードゲームについて研究しています。この研究に興味をもったきっかけは、以前よく見ていたアニメでグラフ理論がでてきたことが最初のきっかけです。大学4年生のときに所属するゼミを選ぶ際、樋口先生のゼミ説明会を聞いてさらに興味を持ちました。特にボードゲームを数学で考えている論文に出会い、面白そうだなと思ってから今の研究を続けています。
グラフ理論は身の回りの現象をモデル化し分析することができます。例えば巡回セールス問題。複数の地点をセールスマンが巡回して、もとに戻るにはどう回るのが最も移動距離が少なくなるか?を考えることが出来ます。これは交通ネットワークや物流ネットワークへの応用が可能です。
学部生のときは数学の中でも代数学、幾何学、解析学など広く数学の分野を学びますが、大学院に進むと自分が興味のあることを好きなだけ突き詰めることができます。それができる環境と時間があることが、大学院に進んでよかったことです。
将来は、日本の行政に携わり、自分の研究や経験をいかして人と社会のためになれるように頑張りたいと思っています。
-
-
今後もチャンスの多い、IT分野へつながる基礎。


-
現在、IT企業のSE(システムエンジニア)として、金融関係のシステムに携わっています。
今年6年目となり、自身の業務領域の拡大と後輩教育に励んでいるところです。主な仕事内容としては、皆さんがクレジットカードを利用する際に必要となる、金融システムの保守・開発です。保守業務としては、システム障害時の調査とリカバリ。開発業務としては、既存システムの改修案件を対応し、設計・製造・試験・リリースなどの一連の開発工程を担当しています。
高校生の頃からIT分野への興味があり、数学科で数値解析を学ぶことで、将来に活かしたいと思っていました。「ITはこれから先も需要が伸びてくる領域であること」、「今後も大きく発展していく分野のため日々新しいスキルが身に付くこと」、「幅広い分野への進出が期待でき、様々な領域と繋がれること」など多くのチャンスがあるため、現在の仕事を選びました。
在学中、4年次のセミナーではプログラミングを使用した数値解析を学び、現在の仕事の基礎が学べたと感じています。
- 2020年3月学習院大学数学科卒業
- 2020年4月株式会社NTTデータ
フィナンシャルテクノロジー
クレジットシステム事業部
-


-
-

- オオシカ ケンイチ
 教授[位相幾何学・離散群]
教授[位相幾何学・離散群]
- 大鹿教授は離散群の幾何を中心として位相幾何学(トポロジー)の研究をしている。一番のテーマとしているのは、3次元双曲多様体とクライン群の位相幾何学的な研究であるが、最近はそれと関連して、タイヒミュラー空間、写像類群なども重要な研究対象としているという。これらは皆長い歴史を持つ研究対象であるが、位相幾何学と複素解析学、幾何学的群論が交錯する分野だそうで、研究において多様な視点を同時に使わなくてはならないところに特に面白みを感じているという。JMSJ論文賞、日本数学会幾何学賞を受賞
-

- オカモト ヒサシ
 教授[数理流体力学・非線型力学]
教授[数理流体力学・非線型力学]
- 岡本教授の興味はふたつある。流体力学と数学史である。力学と言っても物理学や工学よりはずっと数学寄りの研究である。特に、ナヴィエ・ストークス方程式が大好きである。流体力学の研究には解析学や非線形偏微分方程式の知識も必要になるから、そうした分野の研究もしている。数学史は数学史プロパーというよりは、それを現代の大学教育に如何に結びつけるかということを課題としている。井上学術賞、藤原洋数理科学賞、日本応用数理学会業績賞を受賞
-

- タカギ ヒロミチ
 教授[代数幾何・代数多様体の分類]
教授[代数幾何・代数多様体の分類]
- ファノ多様体という複素射影空間における図形を研究している。この19世紀の末に発見された対象の研究を通じて感じられる、代数幾何学における現代的視点と古典的視点の交錯に魅了されている。数学科に入学する皆さん一人ひとりが、数学が得意である、あるいは数学が好きであるという気持ちを在学中にも持ち続けることができるよう手助けすることに使命感を持ち、そのために自分の研究も含めて色々な数学を楽しみ、その喜びを皆さんに伝えていければと願っている。
-
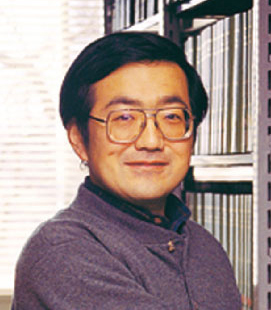
- ナカジマ ショウイチ
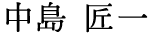 教授[整数論]
教授[整数論]
- 中島教授は、正標数の体の上の代数曲線を研究分野としてきた。これは、整数論的な視点から見た幾何学とも言えるもので、曲線の代数的基本群の性質や被覆のガロア群の表現の決定など、微妙な扱いを要する事柄に力を発揮してきた。これまで整数論と代数幾何学のはざまを彷徨ってきた、と語る教授だが、最近では代数体の岩澤理論など純整数論的な研究も盛んにおこなっている。それでも、整数論の対象である代数体を、代数曲線との類似を通して考えるという視点に魅力を感じているとのこと。本人は(数学者の中では)常識人であることを自負していて、数学の研究成果をいかにわかりやすく伝えるか、ということにも苦心している。
-

- ナカノ シン
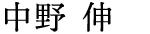 教授[代数的数論]
教授[代数的数論]
- 数論の興味ある問題は、しばしば、代数体の重要な不変量である『イデアル類群』の構造を見ることに帰着されるが、その性質の多くは未だ厚いベールに包まれている。当大学の卒業生である中野教授は、大学院時代から一貫して、代数体のイデアル類群の構造を詳しく調べている。学習院在学中に古典理論をじっくりと勉強できたことが今日の研究に大変役立っている、とのこと。フェルマーの最終定理解決に使われた楕円曲線にも興味を持っているが、それもある特別な代数体の研究から派生したもので、気持ちはつねにイデアル類群にある、と言い訳じみたことを言っている。
-

- ナカムラ シュウ
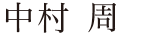 教授[偏微分方程式・数理物理学]
教授[偏微分方程式・数理物理学]
- 中村教授の研究分野は、量子物理学にあらわれる方程式、作用素の数学的解析である。研究に用いる数学的な道具立ては、超局所解析、関数解析、散乱理論、スペクトル理論、と、一見すると高度に専門的な数学に見えるが、証明される数学的な定理は、常に物理現象の理解を目指したものとなっている。特に近年は、古典力学系の幾何学的構造が、半古典極限に限らず、シュレディンガー方程式のさまざまな漸近的ふるまい、例えば解の特異性、散乱現象の性質、などに反映される現象に関して、多数の研究成果を挙げている。日本数学会解析学賞を受賞
-

- ヒグチ ユウスケ
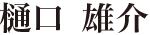 教授[離散大域解析学・グラフ理論]
教授[離散大域解析学・グラフ理論]
- 「グラフという、複数の点とそれらを結ぶ線からなる図形を扱う世界で生れ育ち、今でも戦っている。負けが多いけど」と笑いながら語る樋口教授。グラフという離散図形の上での古典および量子酔歩の挙動や離散シュレディンガー作用素のスペクトル構造を、確率論、函数解析的手法や幾何学的手法のみならずグラフ理論などの組合せ論特有の手法をも用いて解明することが研究対象となっている。最近はより広い分野も意識して、たとえば心的辞書のネットワークとしてのモデル作りや森林景観解析に離散スペクトル解析を応用することにも挑戦しているようである。
-

- ホソノ シノブ
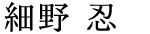 教授[数理物理学・複素多様体]
教授[数理物理学・複素多様体]
- 現代数学と理論物理学が急接近した90年代初頭、純粋数学の研究対象であるカラビ・ヤウ多様体に”弦理論”と呼ばれる理論物理からの新しい視点が加わり、特にミラー対称性という数学者が思いもしなかった不思議な対称性が見つかった。その90年代に研究生活を始めた細野教授は「ミラー対称性に関わる数理現象から数学的事象を読み取る」ことを目標に掲げて、以来精力的に探求を続けている。特に、カラビ・ヤウ多様体の変形族とそれに付随する多変数超幾何微分方程式の性質に関する研究を長く継続している細野教授は、"はやり"の研究に惑わされるのが嫌いな研究者である。日本数学会幾何学賞を受賞
-
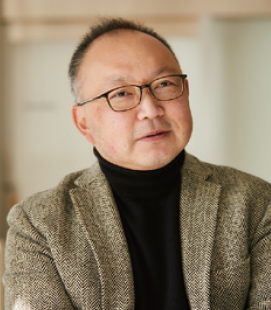
- ヤマダ スミオ
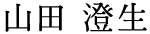 教授[微分幾何学・幾何解析]
教授[微分幾何学・幾何解析]
- いろいろな空間の地図を描くことを仕事とする「幾何学者」である。近代の地図の歴史においては、ガウスから始まりリーマンそしてアインシュタインという立役者たちによって、幾何学という土俵にごく自然に解析学(微分方程式)と物理学(場の理論)が持ち込まれてきた。山田教授もその流れに刺激を受けつつ、一般相対性理論および幾何構造の変形理論という分野を中心に、気になる空間を探し出し、そしてその空間の地図を描いてきた。数学の言葉は時にその高い専門性ゆえに強面であるが、それにひるむことのないように素朴な好奇心を育てることを日々心がけている。
-
